ふと足元を見ると、懸命に列をなす蟻や、光に集まる小さな虫たち。
私たちの身近にいる「虫」たちの姿は、古くから人間の心理や行動を映し出す鏡のような存在でした。
「小さくて弱いもの」「群れるもの」「不快なもの」、あるいは「懸命に生きるもの」。
そんな虫たちの特徴を捉えた言葉は、日常会話の端々で私たちの感情を的確に表現してくれます。今回は、「虫・昆虫」(むし・こんちゅう)にまつわる有名なことわざ、慣用句、故事成語を、意味やシチュエーション別に分類してご紹介します。

- 性格・感情・人間関係
- トラブル・危険・失敗
- 飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)
- 泣きっ面に蜂(なきっつらにはち)
- 虻蜂取らず(あぶはちとらず)
- 蟷螂の斧(とうろうのおの)
- 蜂の巣をつついたよう(はちのすをつついたよう)
- 蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)
- オケラになる(おけらになる)
- 様子・行動・学び
- 頭の上の蝿を追う(あたまのうえのはえをおう)
- 蟻の這い出る隙もない(ありのはいでるすきもない)
- 蛍雪の功(けいせつのこう)
- 夏の虫氷を疑う(なつのむしこおりをうたがう)
- 蝸牛角上の争い(かぎゅうかくじょうのあらそい)
- 虫の息(むしのいき)
- 蚊の鳴くような声(かのなくようなこえ)
- 蜘蛛の子を散らすよう(くものこをちらすよう)
- 蜻蛉返り(とんぼがえり)
- もぬけの殻(もぬけのから)
- 虫の知らせ(むしのしらせ)
性格・感情・人間関係
人の好き嫌いや怒り、臆病さなど、人間の内面や関係性を虫になぞらえた言葉です。
一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
どんなに小さく弱い者にも、それ相応の意地や誇り、思慮分別があること。
弱いからといって侮ってはならないという戒めの言葉です。「一寸」は約3cm、「五分」はその半分を指します。
蓼食う虫も好き好き(たでくうむしもすきずき)
辛くて苦いタデ(蓼)の葉を好んで食べる虫がいるように、人の好みは様々であること。
他人の趣味嗜好を「人それぞれだ」と認める際に使われます。
虫の居所が悪い(むしのいどころがわるい)
これといった理由もないのに、なんとなく機嫌が悪く、ちょっとしたことで怒り出しそうな状態のこと。
人間の体内には「庚申虫(こうしんむし)」など、感情を操る虫がいると考えられていたことに由来します。
虫が好かない(むしがすかない)
相手に明確な非があるわけではないが、生理的に気に入らない、なんとなく好感が持てないこと。
「そりが合わない」に近いニュアンスです。
腹の虫がおさまらない(はらのむしがおさまらない)
怒りや不満がこみ上げてきて、どうしても我慢できない様子。
自分の中で納得がいかず、腹立たしさが鎮まらない状態を表します。
苦虫を噛み潰したよう(にがむしをかみつぶしたよう)
非常に不愉快そうな顔つきや、苦々しい表情の形容。
「苦虫」という種類の虫がいるわけではなく、噛んだら苦そうな虫を想像した表現です。
虫がいい(むしがいい)
自分の都合ばかりを優先し、他人の迷惑を顧みないこと。
身勝手でずうずうしい態度。「そんな虫のいい話は通じない」のように使います。
虫も殺さない(むしもころさない)
虫一匹さえ殺せないほど、性格が優しくおとなしいこと。
また、そのような顔つきをして、実は大胆なことをする人を「虫も殺さない顔をして〜」と評することもあります。
蚤の心臓(のみのしんぞう)
体が小さい蚤(ノミ)のように、気が小さく臆病であること。小心者のたとえとして使われます。
蚤の夫婦(のみのふうふ)
体の大きな妻と、小柄な夫の組み合わせのこと。蚤のメスはオスよりも体が大きいことに由来します。
獅子身中の虫(しししんちゅうのむし)
獅子(ライオン)の体内に寄生して、最強の獅子を死に至らせる虫のこと。
転じて、組織の内部にいながら害を与える裏切り者や、恩を仇で返す者のたとえ。
悪い虫がつく(わるいむしがつく)
未婚の女性に、素行の良くない男性が言い寄ったり、付きまとったりすること。
また、そのような男性と交際を始めること。
本の虫(ほんのむし)
本が大好きで、常に本ばかり読んでいる人のこと。
学問や読書に熱中するあまり、他のことに関心を持たない人を指すこともあります。
蝶よ花よ(ちょうよはなよ)
親が子供(主に娘)を、蝶や花を扱うように大切にかわいがる様子。
苦労をさせず、美しく大事に育てること。「蝶よ花よと育てられる」の形で使われます。
トラブル・危険・失敗
予期せぬ災難や無謀な挑戦、油断が招く失敗などを警告する言葉です。
飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)
明るい光に誘われて虫が火の中に飛び込むように、自ら進んで危険や災難の中に飛び込んでいくこと。
敵の罠に自らはまるような愚かな行動を指します。
泣きっ面に蜂(なきっつらにはち)
泣いてむくんだ顔をさらに蜂が刺すこと。
不運や災難が起きている時に、さらなる不幸が重なることのたとえ。
虻蜂取らず(あぶはちとらず)
アブとハチ、二つの獲物を同時に捕まえようと欲張り、結局どちらも逃してしまうこと。
二つのものを同時に得ようとして失敗するたとえ。
蟷螂の斧(とうろうのおの)
カマキリ(蟷螂)が前足を振り上げて、大きな車輪に立ち向かう様子。
自分の弱さを顧みず、到底かなわない強敵に反抗することのたとえ。無謀な勇気を意味します。
蜂の巣をつついたよう(はちのすをつついたよう)
大勢の人が一斉に騒ぎ出し、収拾がつかなくなる大騒ぎの形容。
蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)
蟻が開けた小さな穴が原因で、巨大な堤防も崩壊してしまうこと。
ほんの些細な油断や不注意が、やがて取り返しのつかない大失敗や損害を引き起こすという教訓。
『韓非子』に見られる言葉です。
オケラになる(おけらになる)
所持金をすべて使い果たし、一文無しになること。
昆虫のオケラ(ケラ)が前足を挙げている姿が、お手上げ状態に見えることから生まれた俗語です。
様子・行動・学び
努力の成果や、儚い様子、視野の狭さを表す表現です。
頭の上の蝿を追う(あたまのうえのはえをおう)
人の世話を焼く前に、まずは自分のことをしっかり始末せよという教訓。
自分自身の頭にたかっているハエさえ追い払えない者が、他人のことをとやかく言うべきではないという意味です。
蟻の這い出る隙もない(ありのはいでるすきもない)
蟻一匹さえ通れないほど、警備や包囲が厳重であること。
少しの隙間もないほど密集している様子を指すこともあります。
蛍雪の功(けいせつのこう)
苦しい環境に負けず、蛍の光や雪明かりで勉強を続けた中国の故事に由来。
苦労して学問に励み、その結果として成功を収めること。「蛍雪」は受験生の象徴的な言葉としても使われます。
夏の虫氷を疑う(なつのむしこおりをうたがう)
自分の狭い知識や経験を絶対的なものと思い込み、未知の広い世界や高い真理を信じようとしないこと。
夏しか生きられない虫は冬の氷を知らないため、その存在を聞かされても「あるはずがない」と疑ってしまうという様子に由来します。古代中国の思想書『荘子』にある言葉です。
蝸牛角上の争い(かぎゅうかくじょうのあらそい)
カタツムリ(蝸牛)の左の角の国と、右の角の国が戦争をするという寓話。
広い宇宙から見れば、人間同士の争いなどちっぽけでつまらないことだというたとえです。
虫の息(むしのいき)
弱った虫のような、今にも絶えそうな呼吸。
病気や怪我などで死にそうな状態、または疲れ果てて活力がない状態を指します。
蚊の鳴くような声(かのなくようなこえ)
蚊の羽音のように、力なく細々とした声。自信がない時や、怯えている時のか細い声の形容です。
蜘蛛の子を散らすよう(くものこをちらすよう)
蜘蛛の卵嚢(袋)が破れ、中の子蜘蛛が一斉に四方八方へ散らばる様子。
大勢の人がまとまりなく、バラバラに逃げ惑う様子のたとえ。
蜻蛉返り(とんぼがえり)
目的地に着いてすぐに用事を済ませ、休む間もなく引き返すこと。
本来はトンボが空中で宙返りすることを指します。
もぬけの殻(もぬけのから)
人が去った後の寝床や住居が空っぽであること。
「もぬけ」とは、セミやヘビが脱皮した後の「抜け殻」のこと。
中身(魂や人)が抜けて外見だけが残っている虚しさを表します。
虫の知らせ(むしのしらせ)
根拠はないが、なんとなく良くないことが起こりそうな予感。
「虫」とは、潜在意識や第六感を指す言葉として使われています。

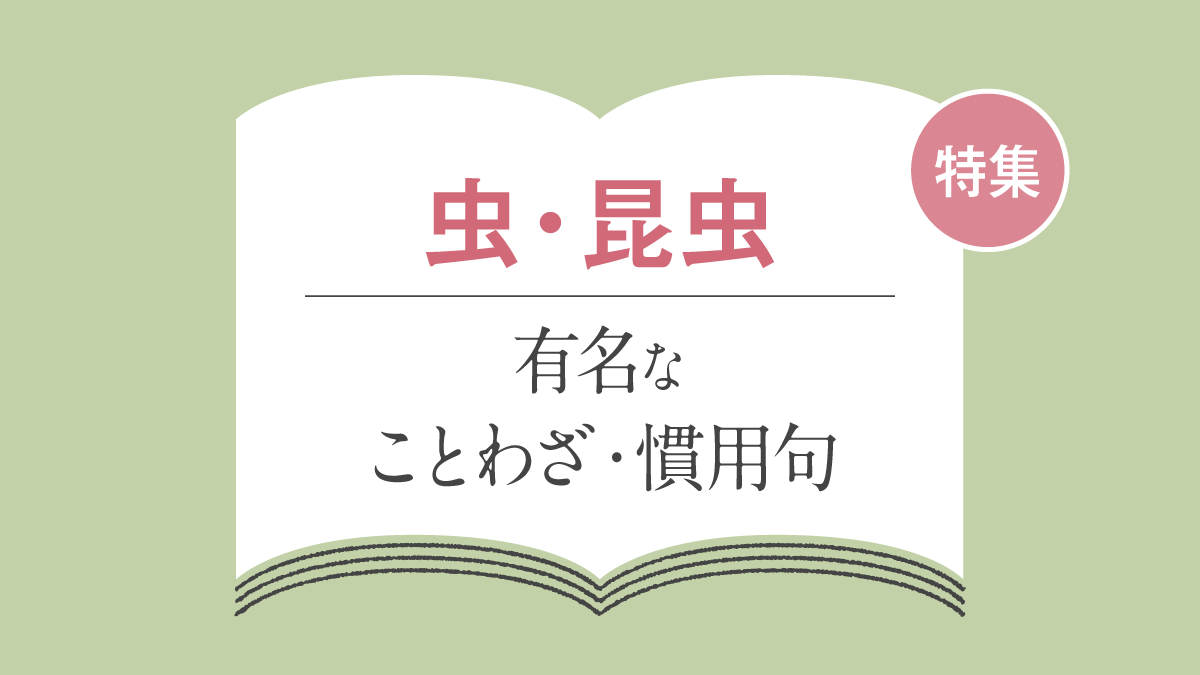







コメント