日本の伝承や言葉の世界において、「鬼」(おに)ほど多面的なキャラクターはいません。
ある時は「恐怖」の象徴、ある時は「最強」の代名詞。
そして時には、人間臭い「愛嬌」や「情け」を見せる存在として描かれます。
ここでは、日常会話でよく使われる有名なものから、少し知的な四字熟語まで、「鬼」にまつわる言葉を意味・シチュエーション別に分類してご紹介します。
- 際立つ「強さ・能力」を表す言葉
- 鬼に金棒(おににかなぼう)
- 神出鬼没(しんしゅつきぼつ)
- 鬼才(きさい)
- 鬼気迫る(ききせまる)
- 〇〇の鬼(まるまるのおに)
- 鬼神(きしん/きじん)
- 意外な「情け・人間味」を表す言葉
- 鬼の目にも涙(おにのめにもなみだ)
- 渡る世間に鬼はなし(わたるせけんにおにはなし)
- 鬼も十八、番茶も出花(おにもじゅうはち、ばんちゃもでばな)
- 鬼手仏心(きしゅぶっしん)
- 「外見と本性・偽善」を表す言葉
- 鬼の空念仏(おにのそらねんぶつ)
- 鬼に衣(おににころも)
- 鬼面人を驚かす(きめんひとをおどろかす)
- 鬼面仏心(きめんぶっしん)
- 「恐怖・不安・疑い」を表す言葉
- 疑心暗鬼(ぎしんあんき)
- 鬼が出るか蛇が出るか(おにがでるかじゃがでるか)
- 百鬼夜行(ひゃっきやこう)
- 魑魅魍魎(ちみもうりょう)
- 悪鬼羅刹(あっきらせつ)
- 鬼哭啾啾(きこくしゅうしゅう)
- 「油断・慢心・態度」を表す言葉
- 鬼の居ぬ間に洗濯(おにのいぬまにせんたく)
- 鬼の首を取ったよう(おにのくびをとったよう)
- 鬼の霍乱(おにのかくらん)
- 来年の事を言えば鬼が笑う(らいねんのことをいえばおにがわらう)
- 心を鬼にする(こころをおににする)
- 天邪鬼(あまのじゃく)
- 親に似ぬ子は鬼の子(おやににぬこはおにのこ)
- 鬼嫁(おによめ)
- 文化・風習にまつわる言葉
- まとめ
際立つ「強さ・能力」を表す言葉
鬼の持つ圧倒的なパワーや、常人離れした才能を称賛・畏怖する言葉です。
鬼に金棒(おににかなぼう)
ただでさえ強い鬼に、さらに武器である金棒を持たせること。
もともと強い者が、良い条件や強力な味方を得て、向かうところ敵なしの強さになることのたとえ。
「虎に翼」「弁慶に薙刀」も同義です。
神出鬼没(しんしゅつきぼつ)
鬼神のように、どこからともなく現れたかと思うと、たちまち消え失せること。
行動が自由自在で、どこに現れるか予測がつかない様子を指します。
鬼才(きさい)
人間とは思えないほど優れた才能のこと。また、その才能を持つ人。
「天才」よりもさらに鋭く、並外れた才知や独特な個性に対する畏敬の念を含んで使われます。
鬼気迫る(ききせまる)
まるでその場に鬼がいるかのような、恐ろしいほどの迫力や気配が漂っている様子。
役者の演技や、真剣勝負の場面などで、見る者を圧倒する凄みを表現します。
〇〇の鬼(まるまるのおに)
「仕事の鬼」「練習の鬼」のように、ある物事に徹底的に打ち込む人。
または「鬼軍曹」「鬼コーチ」のように、妥協を許さない非常に厳しい指導者を指す表現です。
鬼神(きしん/きじん)
荒々しく恐ろしい神、または鬼と神の総称。転じて、人間離れした勇猛さや、すさまじい力を持つ人のたとえとして使われます。
(例:「鬼神のごとき働き」)
意外な「情け・人間味」を表す言葉
冷酷なイメージとは裏腹に、慈悲深さや愛嬌、ギャップを表す言葉です。
鬼の目にも涙(おにのめにもなみだ)
無慈悲で冷酷な鬼でさえ、時には情にほだされて涙を流すことがあるという意味。
普段は厳しい人や冷たい人にも、人間らしい情けや優しさがあることのたとえです。
渡る世間に鬼はなし(わたるせけんにおにはなし)
世の中は無情な人ばかりではなく、困った時には親切に助けてくれる情け深い人も必ずいるということ。
人間不信になりそうな時に、人の世の温かさを説く言葉です。
鬼も十八、番茶も出花(おにもじゅうはち、ばんちゃもでばな)
恐ろしい鬼の娘でも年頃になればそれなりに美しく見え、粗末な番茶でも淹れたては香りが良いこと。
器量よしでなくとも、若い時期には誰にでも魅力があるというたとえ。
※対象をやや下に見るニュアンスが含まれるため、現代では本人に対して使うと失礼になる場合があります。
鬼手仏心(きしゅぶっしん)
手段や方法は鬼のように残酷で厳しく見えるが、その内心や目的は仏のように慈悲深く温かいこと。
「外見と本性・偽善」を表す言葉
見た目と中身の違いや、うわべだけの優しさを皮肉る言葉です。
鬼の空念仏(おにのそらねんぶつ)
普段は無慈悲な人が、うわべだけ慈悲深そうに振る舞うこと。
「鬼の念仏」とも言います。実際には信心などしていないのに、形だけ念仏を唱える様子から、偽善者のたとえとして使われます。
鬼に衣(おににころも)
恐ろしい鬼が僧侶の衣を着て、姿をごまかすこと。
外見は優しそうに見えるが、心の中は鬼のように恐ろしいことのたとえ。
「鬼の空念仏」と似た意味を持ちます。
鬼面人を驚かす(きめんひとをおどろかす)
おもちゃの鬼のお面をつけて人を驚かせるように、外見だけの虚勢を張って、人を威嚇したり驚かせたりすること。実質が伴わないこけおどしを指します。
鬼面仏心(きめんぶっしん)
こちらは良い意味でのギャップです。顔つきは鬼のように怖いが、心は仏のように優しく穏やかであること。
「恐怖・不安・疑い」を表す言葉
得体の知れないものへの恐怖や、疑心暗鬼な心理状態を表す言葉です。
疑心暗鬼(ぎしんあんき)
疑う心があると、何でもないことまで恐ろしく感じたり、怪しく見えたりすること。
「疑心、暗鬼を生ず」の略で、暗闇の中にいないはずの鬼の姿を見てしまう心理を表します。
鬼が出るか蛇が出るか(おにがでるかじゃがでるか)
この先にどんな恐ろしいことや困難が待ち受けているか、全く予測がつかないこと。
「蛇(じゃ)」は大蛇のこと。前途多難で不気味な状況に使われます。
百鬼夜行(ひゃっきやこう)
深夜に多くの妖怪や化け物が列をなして歩き回ること。
転じて、多くの悪人が我が物顔で勝手に振る舞うことのたとえとして使われます。
魑魅魍魎(ちみもうりょう)
山や川などの自然界に潜む、様々な化け物の総称。
転じて、私利私欲のために悪だくみをする得体の知れない連中を指すこともあります。
悪鬼羅刹(あっきらせつ)
人に害をなす恐ろしい化け物。「羅刹」は人を食うとされる悪鬼。
転じて、極めて冷酷で非道な人のたとえ。
鬼哭啾啾(きこくしゅうしゅう)
浮かばれない霊や鬼の泣く声が、恨めしげに響くさま。
「啾啾(しゅうしゅう)」はしくしくと泣く声の形容。転じて、ものすごく気味が悪く、恐ろしい気配が漂うこと。
「油断・慢心・態度」を表す言葉
人の隙や傲慢さ、ひねくれた態度などを、鬼の不在や行動になぞらえた言葉です。
鬼の居ぬ間に洗濯(おにのいぬまにせんたく)
怖い上司や気兼ねする人がいない間に、のんびりとくつろいで息抜きをすること。
「洗濯」は家事のことではなく、命の洗濯(リフレッシュ)を意味します。
鬼の首を取ったよう(おにのくびをとったよう)
大きな手柄を立てて、得意満面で喜ぶ様子のこと。
現代では、相手の小さなミスを指摘して「それ見たことか」と勝ち誇るような、傲慢な態度を批判する文脈でよく使われます。
鬼の霍乱(おにのかくらん)
普段はとても丈夫で病気をしない人が、珍しく体調を崩すこと。
「霍乱(かくらん)」は日射病や食あたりなどの急病のことです。冗談めかして使うことが多い言葉です。
来年の事を言えば鬼が笑う(らいねんのことをいえばおにがわらう)
将来のことは誰にも分からないのだから、あれこれ予測して言っても意味がないということ。
不確かな未来の話を嘲笑う表現です。
「明日のことを言えば鬼が笑う」とも言います。
心を鬼にする(こころをおににする)
相手の将来や成長を思い、あえてかわいそうだと思う気持ち(慈悲心)を抑えて、厳しく接すること。
天邪鬼(あまのじゃく)
わざと人に逆らったり、本心とは裏腹な行動をとったりする、ひねくれた性格の人。
元は仏教守護神に踏みつけられている小鬼の名前です。
親に似ぬ子は鬼の子(おやににぬこはおにのこ)
子供は親に似るのが当たり前である、ということ。
もし似ていないとしたら、それは人間の子ではなく鬼の子だからだ、という逆説的な強調表現です。
鬼嫁(おによめ)
俗語ですが広く定着している言葉。夫に対して非常に厳しく、怖い妻のこと。
愛情の裏返しとして使われることもあれば、単に恐れられている場合もあります。
文化・風習にまつわる言葉
鬼門(きもん)
北東の方角のこと。陰陽道で「鬼が出入りする不吉な方角」とされ、忌み嫌われます。
転じて、自分が苦手とする相手や場所、どうしても上手くいかない事柄のことも指します。
鬼籍に入る(きせきにはいる)
死ぬこと。亡くなった人の名は閻魔大王の帳面(鬼籍)に記載されるという俗説から。
鬼瓦(おにがわら)
屋根の棟(むね)の端などに設置される、鬼の顔をかたどった瓦。
怖い顔で睨みをきかせ、厄災が家に入ってこないようにする「魔除け」の役割を持ちます。
鬼ごっこ
じゃんけんなどで決めた「鬼」が、逃げる他の子を追いかけて捕まえる遊び。
古来より、異界の存在である「鬼」に捕まると、その役が交代するという象徴的な意味合いを含んでいます。
まとめ
怖い顔をしていても、ふとした瞬間に涙を見せる。そんな「鬼」の姿は、どこか私たち人間そのものと重なるところがあるのかもしれません。
厳しさの中に愛情を込めたり、強がっていても実は不安だったり。 言葉の世界に生きる鬼たちは、恐ろしいだけではなく、どこか憎めない隣人のようにも思えてきますね。






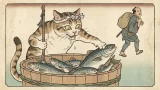
コメント