会議でのプレゼンテーションや営業トークなど、つっかえることなくすらすらと話す人の様子を見て、
「まるで立て板に水だ」と感心したことはありませんか?
この言葉は、流れるような話しぶりを称賛する際によく使われますが、場面によっては「口が達者すぎる」という皮肉を含んで使われることもあります。
「立て板に水」の意味
「立て板に水」とは、すらすらとよどみなく話すことのたとえです。
- 立て板(たていた):垂直に立てかけた板のこと。
- 水(みず):液体。
板を平らな場所に置いて水を流すと、水はゆっくりと広がります。
しかし、板を垂直に立てて水を流すと、水は何の障害もなく一気に下まで流れ落ちます。
この様子を、言葉が次から次へと口から出てくる様子に重ね合わせています。
単に「話すのが速い(早口)」という意味ではなく、つかえたり、言いよどんだりしない「流暢さ」に焦点を当てた言葉です。
「立て板に水」の語源・由来
この言葉は、自然現象を観察した比喩として古くから日本で使われています。
鎌倉時代から続く表現
「立て板に水」という表現自体は古く、鎌倉時代の『源平盛衰記』にも「流れの早きこと立て板に水を懸くるに似たり」という記述が見られます。
当時は話し方に限らず、「物事の進みが非常に速いこと」のたとえとして使われていました。
時を経て、室町時代の狂言などでは弁舌の滑らかさを表す言葉として定着していきました。
「上方いろはかるた」で有名に
江戸時代、子供たちの間で流行した「いろはかるた」には、地域によってバリエーションがありました。
江戸(東京)の「犬棒かるた」では、「た」の読み札は「旅は道連れ世は情け」ですが、京都や大阪を中心に普及した「上方いろはかるた」では、「た」の読み札として「立て板に水」が採用されています。
これにより、西日本を中心に広く庶民の間に浸透しました。
「立て板に水」の使い方・例文
主に、アナウンサーの実況、落語家の語り、熟練のセールスマンのトークなど、話しぶりが非常に滑らかであることを表現する際に使われます。
例文
- その実演販売士の説明は、まさに立て板に水で、思わず商品を買ってしまった。
- 彼は緊張する様子もなく、立て板に水の如くスピーチを行い、聴衆を魅了した。
- 彼女の弁明は立て板に水だったが、あまりに流暢すぎてかえって誠実さが感じられなかった。
使用上の注意点
基本的には「話が上手」という褒め言葉として使われます。しかし、文脈によっては「口先だけで中身がない」「調子が良すぎる」といったネガティブなニュアンス(皮肉)を含んで使われる場合があります。
特に、謝罪や反省が求められる場面で「立て板に水」のように弁解すると、「反省の色が見えない」「口が達者なだけ」と捉えられるリスクがあるため注意が必要です。
「立て板に水」の類義語・関連語
流暢に話す様子を表す言葉はいくつかありますが、ニュアンスが微妙に異なります。
- 懸河の弁(けんがのべん):
「懸河」は滝のような急流のこと。立て板に水と同様に、よどみなく話すことのたとえ。
こちらはより勢いが激しく、圧倒されるような弁舌に対して使われることが多いです。 - 弁舌さわやか(べんぜつさわやか):
話の運びが明快で、聞いていて気持ちが良いこと。ポジティブな意味合いが強く、皮肉で使われることはあまりありません。 - 舌を巻く(したをまく):
相手の能力に驚き、感心すること。話術に限らず使われますが、「彼の話術には舌を巻く」のように使われることがあります。
「立て板に水」の対義語
「よどみなく話す」の反対、つまり「つっかえながら話す」様子を表す言葉です。
- 訥弁(とつべん):
話し方がなめらかでなく、つかえがちなこと。ただし、「訥弁」は必ずしも悪い意味ではなく、誠実な人柄を表す言葉として肯定的に使われることもあります(「訥弁だが誠実な人」など)。 - 横板に雨垂れ(よこいたにあまだれ):
「立て板に水」をもじった言葉。板を横にすると水がたまり、雨垂れのようにポツリポツリとしか落ちないことから、話がなめらかに進まない様子のたとえ。
「立て板に水」の英語表現
英語でも、水や流れにたとえた表現や、滑らかさを強調する表現があります。
fluent
- 意味:「流暢な」「堪能な」
- 解説:最も一般的でニュートラルな表現です。
- 例文:
He is a fluent speaker.
(彼は流暢な話し手だ=立て板に水だ)
talk a blue streak
- 意味:「立て板に水のようにしゃべりまくる」
- 解説:稲妻(blue streak)のように速く、絶え間なくしゃべり続ける様子を表す慣用句です。
- 例文:
She talked a blue streak about her trip.
(彼女は旅行について、立て板に水のごとくしゃべりまくった)
「立て板に水」に関する豆知識
江戸と上方、かるたの違い
由来の項でも触れましたが、「いろはかるた」には地域差があります。
- 江戸(犬棒かるた):「た」=旅は道連れ世は情け
- 上方(京かるた):「た」=立て板に水
- 尾張(名古屋):「た」=玉磨かざれば光なし(※諸説あり)
このように、「立て板に水」は元々関西圏のいろはかるたに収録されていた言葉です。
もしあなたが関西出身で「『た』といえば『立て板に水』でしょ?」と思っていたなら、それは上方文化の影響を強く受けている証拠かもしれません。
まとめ – 流暢さと誠実さ
立て板に水は、よどみなく話す技術の高さや、頭の回転の速さを表す言葉です。
プレゼンやスピーチでは目指すべき姿の一つですが、会話においては、あまりに流暢すぎると「心がこもっていない」と思われることもあります。
時には言葉を選びながらゆっくり話すほうが、相手の心に届くこともあるかもしれません。
場面に応じて、水の流れを調整できるのが、本当の話し上手と言えるでしょう。




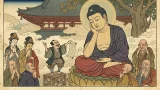

コメント