私たちの周りには、動物にまつわる多くのことわざや慣用句が存在します。中でも、ヘビ(蛇)、カエル(蛙)、トカゲ(蜥蜴)、カメ(亀)といった爬虫類や両生類は、その独特な生態や姿から、昔から様々な教訓や比喩表現に用いられてきました。
これらの言葉は、時に人間の本質を鋭く突いたり、状況を的確に表現したりする知恵として受け継がれています。
「爬虫類・両生類」に関連する言葉
「ヘビ・カエル・トカゲ」といった爬虫類や両生類というテーマに関連する、主なことわざや慣用句、四字熟語などを、生き物別に分類して紹介します。
ヘビ(蛇)に関連する言葉
- 蛇の道は蛇(じゃのみちはへび):
同類の者どうしは、互いのすることがよくわかるというたとえ。 - 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる(じゃにかまれてくちなわにおびじる):
一度ひどい目に遭うと、それに似たものを見ただけで怖がるようになることのたとえ。 - 蛇に睨まれた蛙(へびににらまれたかえる):
恐怖ですくんでしまい、身動きがとれなくなることのたとえ。 - 蛇の生殺し(へびのなまごろし):
物事に決着をつけず、中途半端な状態で相手を苦しめること。 - 藪をつついて蛇を出す(やぶをつついてへびをだす):
余計なことをして、かえって災いを招くことのたとえ。「藪蛇(やぶへび)」とも言います。 - 長蛇の列(ちょうだのれつ):
蛇のように長く(長蛇)うねうねと続いている行列のこと。 - 蛇蝎の如く嫌う(だかつのごとくきらう):
まるでヘビやサソリ(蝎)を見るように、非常に強く嫌うこと。 - 打草驚蛇(だそうきょうだ):
草を打って蛇を驚かす意から、一方を罰することで、他方に警告を与えること。また、余計なことをして相手に感づかれること。 - 竜頭蛇尾(りゅうとうだび):
初めは竜の頭のように勢いが盛んだが、終わりは蛇の尾のように振るわなくなること。 - 蛇心仏口(じゃしんぶっこう):
心は蛇のように邪悪だが、口では仏のように親切なことを言うこと。 - 蛇足(だそく):
あっても益がない、余計なもの。蛇の絵に足を書き加えて台無しにした故事から。 - 杯中の蛇影(はいちゅうのだえい):
盃に映った蛇の影を本物と思い込み病気になった故事から、疑いの心が生じると、何でもないことにもおびえることのたとえ。
カエル(蛙)に関連する言葉
(※カエルは両生類に分類されます)
- 蛙の子は蛙(かえるのこはかえる):
子は親に似るもので、平凡な親から非凡な子は出ないというたとえ。 - 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず):
ごく狭い世界や知識にとらわれ、広い世界があることを知らないことのたとえ。 - 蛙の面に水(かえるのつらにみず):
どんな仕打ちを受けても、まったく平気でいることのたとえ。 - 蛙の行列(かえるのぎょうれつ):
まとまりがなく、ばらばらな行列や集団のこと。 - 茹でガエル(ゆでガエル):
緩やかな環境変化に対応できず、危機に気づかないことのたとえ。
トカゲ(蜥蜴)に関連する言葉
(※トカゲは爬虫類に分類されます)
- トカゲの尻尾切り(とかげのしっぽきり):
本体を守るため、あるいは事態を収拾するために、一部分を切り捨てて逃げること。
カメ(亀)・スッポン(鼈)に関連する言葉
(※カメ・スッポンは爬虫類に分類されます)
- 亀の甲より年の劫(かめのこうよりとしのこう):
亀の硬い甲羅よりも、長く生きてきた経験(年の功)のほうが確かで尊いということ。 - 鶴は千年、亀は万年(つるはせんねんかめはまんねん):
長寿でめでたいことのたとえ。 - 亀毛兎角(きもうとかく):
亀に毛が生え、兎に角が生える意から、現実にはあり得ないことのたとえ。 - 月とスッポン(つきとすっぽん):
二つのものの間に大きな差があり、比べものにならないことのたとえ。
ワニ(鰐)に関連する言葉
(※ワニは爬虫類に分類されます)
- ワニの涙(わにのなみだ):
偽りの涙や、見せかけの同情のこと。
まとめ – 爬虫類・両生類に関連する言葉を学ぶ
ヘビ、カエル、カメなどの爬虫類・両生類に関連する言葉には、それぞれの生き物が持つイメージが色濃く反映されています。
恐怖や災い(蛇)、狭い世界(蛙)、長寿や経験(亀)、あるいは自己防衛(トカゲ)など、実に多様な教訓や比喩が込められています。これらの言葉は、人間社会や心理を鋭く捉える、先人たちの知恵と言えるでしょう。


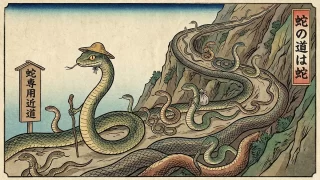



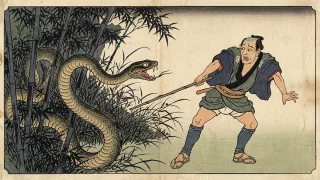

コメント