真に価値のあるものは大切に仕舞い込まれ、表舞台には質の劣るものばかりが溢れてしまうことがあります。
善いものが報われるべきだという期待に反し、劣悪なものが勢力を強めていく不条理。
そんな状況を、「悪貨は良貨を駆逐する」(あっかはりょうかをくちくする)と言います。
意味・教訓
「悪貨は良貨を駆逐する」とは、額面が同じで実質的価値が異なる二種類の貨幣が流通すると、人々は価値の高い「良貨」を手元に蓄え、価値の低い「悪貨」を支払いに使うため、市場に質の悪い貨幣だけが残るという法則を指します。
現在では経済の枠組みを超え、「劣ったものがはびこることで、優れたものが排除される」という社会現象や組織の腐敗を批判する際にも用いられます。
- 悪貨(あっか):
素材としての価値を意図的に下げた質の悪い貨幣。 - 良貨(りょうか):
素材そのものに十分な価値がある質の良い貨幣。 - 駆逐(くちく):
邪魔なものを追い払うこと。
語源・由来
「悪貨は良貨を駆逐する」の由来は、16世紀のイギリス国王エリザベス1世に仕えた財政家、サー・トーマス・グレシャムが提唱した「グレシャムの法則」にあります。
当時のイギリスでは、財政難を補うために金の純度を下げた質の悪い貨幣が発行されました。
すると人々は、純度の高い「良貨」を地金として溶かしたり貯蔵したりして、市場には「悪貨」だけを流すようになりました。
この状況をグレシャムが女王への書簡で指摘したことが起源とされています。
この現象は古代から知られており、紀元前405年のアリストパネスの喜劇『蛙』にも、立派な硬貨が避けられ質の悪い銅貨ばかりが使われる状況の記述が見られます。
使い方・例文
「悪貨は良貨を駆逐する」は、経済現象の説明だけでなく、質の低いものが蔓延して優れたものが排除される状況全般で用いられます。
主に組織の腐敗、情報の劣化、市場の質の低下などを批判・警告する文脈で使われます。
例文
- 不確かな噂の拡散は、まさに悪貨は良貨を駆逐する典型だ。
- 実力者が去った今の職場は、悪貨は良貨を駆逐する状態にある。
- 派手な意見ばかりが通り、悪貨は良貨を駆逐するように誠実な案が消えた。
誤用・注意点
「悪貨は良貨を駆逐する」を、「悪いことをすれば報いを受ける」といった勧善懲悪の意味で使うのは間違いです。
あくまで「質の悪いものが優勢になり、良いものが排除される」という、価値の逆転現象を指す言葉です。
また、この言葉は現状を肯定するものではなく、批判的なニュアンスを含みます。
特定の集団を指して「悪貨」と呼ぶことは、相手を強く否定することに繋がるため、慎重な判断が求められます。
類義語・関連語
「悪貨は良貨を駆逐する」と似た意味を持つ言葉や、関連する学術的な概念には以下のようなものがあります。
- グレシャムの法則:
「悪貨は良貨を駆逐する」の別名であり、経済学においてこの現象を指す正式な名称。 - レモン市場:
売り手と買い手の情報格差(情報の非対称性)により、質の高い商品が排除され、劣悪な商品やサービスばかりが流通してしまう現象。
1970年に経済学者ジョージ・アカロフが、中古車市場を例に「逆選択」の仕組みとして提唱した。 - 逆選抜(ぎゃくせんばつ):
情報の格差がある状況下で、本来選ばれるべき優れた対象ではなく、むしろ望ましくない劣った対象が選ばれてしまうこと。 - 正直者が馬鹿を見る(しょうじきものがばかをみる):
正当に努力する者や規則を守る者が損をし、狡賢く立ち回る者が利益を得る不条理な社会状況。
対義語
「悪貨は良貨を駆逐する」とは対照的な、優れたものが正当に評価されたり、悪いものが除かれたりする状況を指す言葉には、以下のようなものがあります。
- ティアーズの法則:
通貨の価値が極端に不安定になった際、人々が質の悪い貨幣を拒絶して信頼できる貨幣を求めるため、良貨が悪貨を駆逐する現象。 - 淘汰(とうた):
不必要なものや質の劣るものが取り除かれ、優れたものや適したものだけが残ること。 - 自然淘汰(しぜんとうた):
環境に適応した優れたものが生き残り、適さないものが自然に消えていくプロセス。 - 正直者は報われる(しょうじきものはむくわれる):
不正をせず誠実に努力する人が、最終的には正当な評価や幸福を得るべきだという考え。
英語表現
「悪貨は良貨を駆逐する」を英語で表現する場合、以下の定型表現が用いられます。
Bad money drives out good.
「悪貨は良貨を追い出す」
直訳通りの表現であり、英語圏でも非常に一般的なことわざとして定着しています。
- 例文:
- In the information age, bad money drives out good, as fake news spreads faster.
(情報化社会では、悪貨は良貨を駆逐するように、偽ニュースの方が早く広まる。)
Gresham’s Law.
「グレシャムの法則」
学術的、あるいは知的な文脈で、現象そのものを指し示す際に使われます。
- 例文:
- We must ensure that Gresham’s Law doesn’t take hold in our workplace.
(職場にグレシャムの法則が根付かないようにしなければならない。)
偽造を防ぐための工夫
かつての貨幣は、金や銀そのものの重さが価値でした。
狡猾な人々は金貨の縁を少しずつ削り取って地金を盗み、残った軽い貨幣(悪貨)を市場で使い、削られていない重い金貨(良貨)を溜め込みました。
これに対抗するため、金貨の縁に「ギザギザ」を入れる工夫がなされました。
削ればすぐに分かるようにしたこの工夫が、現在の50円玉や100円玉に残っている側面のギザギザのルーツです。
「悪貨」の流通を物理的に防ごうとした先人の知恵が、今も私たちの手元に残っています。
まとめ
「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉は、個人の合理的な選択が、意図せず全体を劣化させてしまうという社会の皮肉を突いています。
楽な方へ流されたり、目立つ情報に飛びついたりする心理は、誰の心にも潜んでいるのかもしれません。
しかし、このメカニズムを知ることは、物事の本質的な価値を見極める助けとなります。
一人一人が意識的に「良質」なものを選び取ることで、社会や組織の質を保つことができると言えるかもしれません。






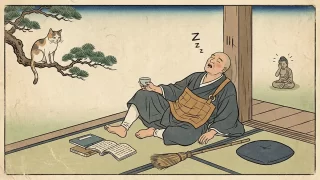
コメント