「河童の川流れ」(かっぱのかわながれ)のように、現実には存在しないはずの架空の生き物が、私たちの会話の中に生き生きと息づいています。
河童、天狗、麒麟……。
古くから伝説や物語の中で描かれてきた彼らは、時に恐ろしい怪物として、時に神聖な使いとして、人々の想像力をかき立ててきました。
その強烈な個性は、人間の性質や世の中の道理を説く「ことわざ」や「四字熟語」として、現代にも数多く残されています。
ここでは、そんな架空・伝説上の生物にまつわる有名な言葉を、生物ごとに整理してご紹介します。
※「龍」や「鬼」も架空の生物ですが、ページ最下部にて別記事で詳しく解説しています。
- 河童(かっぱ)のことば
- 河童の川流れ(かっぱのかわながれ)
- 陸に上がった河童(おかにあがったかっぱ)
- 河童に水練(かっぱにすいれん)
- 屁の河童(へのかっぱ)
- 天狗(てんぐ)のことば
- 天狗になる(てんぐになる)
- 天狗の鼻を折る(てんぐのはなをおる)
- 天狗の飛び損ない(てんぐのとびそこない)
- 麒麟(きりん)・鳳凰(ほうおう)のことば
- 麒麟も老いては駑馬に劣る(きりんもおいてはどばにおとる)
- 麒麟児(きりんじ)
- 鳳鳴朝陽(ほうめいちょうよう)
- 伏龍鳳雛(ふくりゅうほうすう)
- その他(天邪鬼・えぬ・閻魔など)
- まとめ
河童(かっぱ)のことば

河童とは、日本の川や沼に住むとされる妖怪、あるいは水神の一種です。
頭には水が入った皿があり、背中には甲羅、手足には水かきを持つ姿で描かれます。
泳ぎが得意で、相撲やキュウリを好むという愛嬌のある一面も持ち合わせています。
河童の川流れ(かっぱのかわながれ)
泳ぎの名人である河童でさえ、時には水に流されてしまうこと。
どんな達人や名人でも、時には失敗することがあるというたとえです。
「猿も木から落ちる」「弘法にも筆の誤り」と同じ意味で使われます。
陸に上がった河童(おかにあがったかっぱ)
水中では無敵の河童も、陸の上では力が弱まってしまうことから、自分に合った環境を離れ、全く実力を発揮できなくなる様子のこと。
哀れな状況や、無力な様子を表す際によく使われます。
河童に水練(かっぱにすいれん)
泳ぎが得意な河童に泳ぎ方を教えるような行為。
自分よりはるかに詳しい人に教えようとする愚かさや、無駄な行為のたとえ。
「釈迦に説法」と同義です。
屁の河童(へのかっぱ)
物事が非常に簡単で、取るに足りないこと。「そんなことは屁の河童だ」のように使います。
由来には諸説ありますが、「河童の屁」は水中で勢いがなく頼りないことから、大したことではないという意味になったとする説や、「木っ端の火(こっぱのひ)」がなまったとする説などが知られています。
天狗(てんぐ)のことば

天狗は、日本の山奥に住むとされる伝説上の怪物です。
赤ら顔に高い鼻、山伏の姿をして背中に翼を持ち、空を自由に飛び回ると言われます。
強力な神通力を持つ一方で、その高い鼻は「慢心」や「高慢」の象徴とされています。
天狗になる(てんぐになる)
自分の能力を過信し、うぬぼれている状態。人を見下したような態度をとること。
「彼は昇進してから天狗になっている」のように、批判的な意味を込めて使われます。
天狗の鼻を折る(てんぐのはなをおる)
得意になって威張っている相手をやり込め、その慢心をくじくこと。
単に「鼻を折る」「鼻をへし折る」とも言います。
天狗の飛び損ない(てんぐのとびそこない)
神通力のある天狗でも、飛び立つ際に失敗することがあるということ。
名人も時には失敗するという意味で、「河童の川流れ」と似た意味を持ちます。
麒麟(きりん)・鳳凰(ほうおう)のことば


中国神話に由来する「聖なる獣」たちです。これらは優れた人物や、平和な世の中の象徴として扱われます。
麒麟も老いては駑馬に劣る(きりんもおいてはどばにおとる)
麒麟は、一日に千里を走るとされる想像上の名馬(または聖獣)。
そんな麒麟も、年老いてしまえば、足の遅い馬(駑馬)にも負けてしまうということ。
どんなに優れた人も、老いには勝てず能力が衰えるという、世の無常を説いた言葉です。
麒麟児(きりんじ)
才能が優れ、将来が期待される少年のこと。
幼い頃から飛び抜けた才能を示す子供を指して使います。「神童」に近い言葉です。
鳳鳴朝陽(ほうめいちょうよう)
鳳凰が朝日に向かって鳴くこと。
世の中が平和で、優れた才能を持つ人が現れる前兆を意味する、非常におめでたい四字熟語です。
伏龍鳳雛(ふくりゅうほうすう)
世に隠れているが、時が来れば英雄となる才能を持った若者のこと。
「伏龍」は水に潜んでいる龍、「鳳雛」は鳳凰のひなを指します。
『三国志』において、諸葛孔明と龐統を指した言葉として有名です。
その他(天邪鬼・えぬ・閻魔など)
天邪鬼(あまのじゃく)
わざと人の言動に逆らったり、本心とは裏腹な態度をとったりするひねくれ者のこと。
元々は「天探女(あまのさぐめ)」という日本神話の悪神や、仏教で毘沙門天に踏みつけられている小鬼に由来します。
鵺のような(ぬえのような)
鵺は、頭は猿、体は狸、手足は虎、尾は蛇という姿をした伝説の怪物です。
その姿から転じて、正体がはっきりせず、つかみどころのない人物や物事のたとえに使われます。
「鵺のような人だ」と言えば、何を考えているか分からず不気味だというニュアンスになります。
嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる
(うそをつくとえんまさまにしたをぬかれる)
閻魔は、地獄で死者の罪を裁く大王。
嘘をついた者は、死後に地獄で閻魔大王にやっとこで舌を抜かれるという言い伝えから、嘘をついてはいけないという戒めとして使われます。
借りる時の地蔵顔、返す時の閻魔顔
(かりるときのじぞうがお、かえすときのえんまがお)
お金を借りる時は地蔵のように柔和で愛想が良いが、いざ返す段になると、閻魔大王のように恐ろしい顔をして渋ること。
人間のお金に対する身勝手さや、現金な態度を皮肉ったことわざです。
(※古くは「返す」を「済(な)す」と言いました)
まとめ
河童、天狗、麒麟といった架空の生物たちは、単なる空想の産物ではなく、人間界の複雑な感情や真理を、私たちに分かりやすく伝えるための「器」として機能してきました。
「慢心」を天狗で表し、「無常」を老いた麒麟で表す。
彼らの姿を思い浮かべながら言葉を使うことで、会話に彩りと深みが生まれることでしょう。

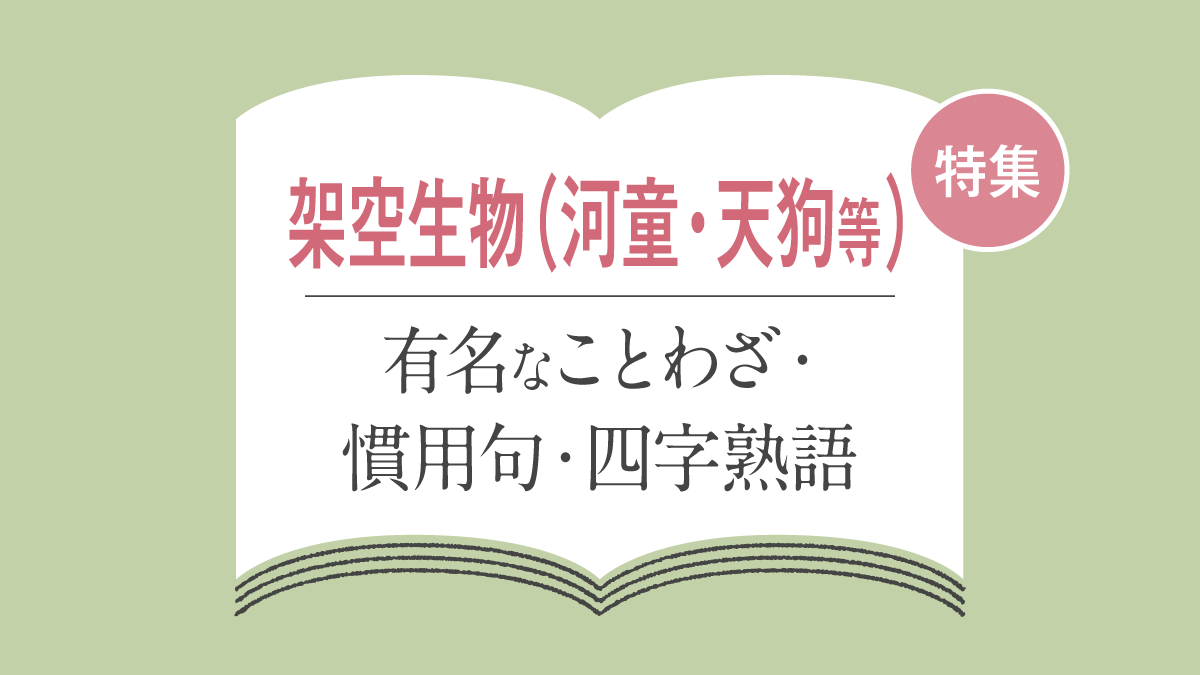







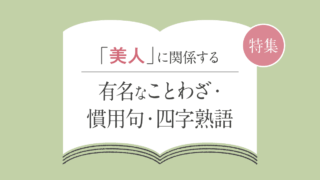

コメント