私たちの暮らしを彩る花や、日々の食卓に並ぶ野菜や果物。
古くから日本人は、これら身近な自然の姿に人生の教訓や人間の機微を重ね合わせてきました。
四季折々の変化を見せる植物たちは、時に厳しく、時に優しく、私たちが生きていく上での知恵を授けてくれます。
ここでは、そんな「花・植物・野菜・果物」にまつわる言葉を、意味や使う場面ごとに整理してご紹介します。

- 人生の教訓・心構え(成功・努力・謙虚)
- 実るほど頭を垂れる稲穂かな(みのるほどこうべをたれるいなほかな)
- 栴檀は双葉より芳し(せんだんはふたばよりかんばし)
- 桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)
- 蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)
- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿(さくらきるばか、うめきらぬばか)
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
- 芽が出る(めがでる)
- 一花咲かせる(ひとはなさかせる)
- 人間関係・評価(美しさ・個性・評価)
- 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花(たてばしゃくやくすわればぼたんあるくすがたはゆりのはな)
- いずれ菖蒲か杜若(いずれあやめかかきつばた)
- 高嶺の花(たかねのはな)
- 蓼食う虫も好き好き(たでくうむしもすきずき)
- 瓜二つ(うりふたつ)
- 瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ)
- 竹を割ったよう(たけをわったよう)
- 柳は緑、花は紅(やなぎはみどり、はなはくれない)
- 梅に鶯(うめにうぐいす)
- 羞花閉月(しゅうかへいげつ)
- 桜梅桃李(おうばいとうり)
- 棘がある(とげがある)
- 世の中の理・情景(勢い・変化・無常)
- 破竹の勢い(はちくのいきおい)
- 雨後の筍(うごのたけのこ)
- 世の中は三日見ぬ間の桜かな(よのなかはみっかみぬまのさくらかな)
- 一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる)
- 落花流水(らっかりゅうすい)
- 花鳥風月(かちょうふうげつ)
- 柳緑花紅(りゅうりょくかこう)
- 柳暗花明(りゅうあんかめい)
- 草木も眠る丑三つ時(そうもくもねむるうしみつどき)
- 鏡花水月(きょうかすいげつ)
- 花に十日の紅なし(はなにとおかのくれないなし)
- 花に嵐(はなにあらし)
- 状況の比喩・暮らし(意外・混雑・便り)
- 瓢箪から駒(ひょうたんからこま)
- 火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう)
- 青菜に塩(あおなにしお)
- 梨の礫(なしのつぶて)
- 芋を洗うよう(いもをあらうよう)
- 鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる)
- 根も葉もない(ねもはもない)
- 根掘り葉掘り(ねほりはほり)
- 徒花(あだばな)
- 種を明かす(たねをあかす)
- 鳩に豆鉄砲(はとにまめでっぽう)
- 胡麻をする(ごまをする)
- 花が咲く(はながさく)
- 竹馬の友(ちくばのとも)
- 注意・教訓・失敗(油断・手遅れ・勘違い)
- 李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)
- 花より団子(はなよりだんご)
- 枯れ木も山の賑わい(かれきもやまのにぎわい)
- 六日の菖蒲十日の菊(むいかのあやめとおかのきく)
- 木を見て森を見ず(きをみてもりをみず)
- 葦の髄から天井を覗く(あしのずいからてんじょうをのぞく)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 大根役者(だいこんやくしゃ)
- 言わぬが花(いわぬがはな)
- 木を隠すなら森の中(きをかくすならもりのなか)
- 柳に風(やなぎにかぜ)
- 木に竹を接ぐ(きにたけをつぐ)
- 道草を食う(みちくさをくう)
- 花を持たせる(はなをもたせる)
- 意外な効果・環境(健康・恐怖・影響)
- 柿が赤くなれば医者が青くなる(かきがあかくなればいしゃがあおくなる)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 草木皆兵(そうもくかいへい)
- 五穀豊穣(ごこくほうじょう)
- 橘化して枳となる(たちばなげしてカラタチとなる)
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 枯れ木に花咲く(かれきにはなさく)
- 錦上花を添える(きんじょうはなをそえる)
- 一木一草(いちぼくいっそう)
- 桃李もの言わざれども、下自ら蹊を成す(とうりものいわざれども、したおのずからこみちをなす)
- 草の根分けても(くさのねわけても)
- 草葉の陰(くさばのかげ)
- 両手に花(りょうてにはな)
- 茶を濁す(ちゃをにごす)
- 花道を飾る(はなみちをかざる)
人生の教訓・心構え(成功・努力・謙虚)
実るほど頭を垂れる稲穂かな(みのるほどこうべをたれるいなほかな)
稲の穂が熟すと自重で低く垂れ下がる様子を、人格の完成した人物に例えた句。学問や徳行が深まるほど、他人に対して傲慢にならず、より謙虚に振る舞うべきだという戒めを指す。
栴檀は双葉より芳し(せんだんはふたばよりかんばし)
白檀(びゃくだん)は発芽した時期からすでに特有の芳香を放つ。大成する才能の持ち主は、幼少時からすでに常人とは異なる優れた片鱗を見せているという例え。
桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)
植樹から結実までにかかる歳月を示し、何事も一人前として成果を収めるには、相応の年月と忍耐が必要であるという教訓。物事の習熟には一定の期間を要する道理を説く。
蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)
種を蒔かなければ収穫が得られないように、努力という原因なしに、成功という結果を期待することはできない。因果応報の理を説き、自らの行動を促す際に用いられる。
桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿(さくらきるばか、うめきらぬばか)
桜は枝を切ると腐敗しやすく、梅は剪定しなければ良い花実がつかない。それぞれの植物の個性に合わせた手入れが必要なことから、教育や管理において対象の性質を正しく見極めて対応すべきであるとの教え。
青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
藍草から抽出した染料が、原料よりも鮮やかな青色になる事実に基づく。弟子が師匠の教えを受けて努力した結果、師匠よりも優れた才能や実力を備えること。
芽が出る(めがでる)
草木が芽吹くように、長期間の下積みや努力がようやく認められ、成功への明るい兆しが見えてくる状況。また、勝負事などで幸運が巡ってくることも表す。
一花咲かせる(ひとはなさかせる)
人生において一度、華々しい成功を収める。一時的であっても世間にその名を轟かせ、得意の絶頂を謳歌する様子。
人間関係・評価(美しさ・個性・評価)
立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花(たてばしゃくやくすわればぼたんあるくすがたはゆりのはな)
すらりと伸びた芍薬、華やかに広がる牡丹、風に揺れる百合。美しい女性の容姿やしなやかな立ち居振る舞いを、それぞれの花が持つ最高の美しさに例えた賛辞。
いずれ菖蒲か杜若(いずれあやめかかきつばた)
菖蒲(あやめ)も杜若(かきつばた)も姿が似ており、どちらも美しく優劣をつけがたい。優れたものが二つ並んでおり、選択に苦慮するほど甲乙つけがたい状況をいう。
高嶺の花(たかねのはな)
高い山の断崖に咲く花のように、遠くから眺めるだけで、自分には到底手に入れることができない憧れの対象。能力や地位の差があり、親しくなることが困難な人物の例え。
蓼食う虫も好き好き(たでくうむしもすきずき)
辛くて苦い蓼(たで)の葉を好んで食べる虫がいるように、人の好みは千差万別。一般的でない趣味や嗜好を持つ者がいても、それを否定できないという道理。
瓜二つ(うりふたつ)
瓜を縦に二つ割りにした切り口が酷似している様子。親子や兄弟などの顔立ちが、見分けがつかないほど非常によく似ていることを表す。
瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ)
平凡な親から非凡な子は生まれにくい。血筋や素質は嘘をつかないもので、原因に応じた結果しか現れないことの冷徹な例え。
竹を割ったよう(たけをわったよう)
竹が縦にパッと真っ直ぐ割れる性質。性格に裏表がなく、未練がましくない。気性がまっすぐで潔い人物の形容。
柳は緑、花は紅(やなぎはみどり、はなはくれない)
春の情景をありのままに捉えた言葉。柳は緑色、花は紅色であるのが自然の姿であり、物事にはそれぞれ固有の個性や真理があるという考え。
梅に鶯(うめにうぐいす)
梅の枝に鶯が止まる様子は非常に調和がとれていて美しい。取り合わせが良いものや、非常に仲の良い間柄を指す定番の比喩。
羞花閉月(しゅうかへいげつ)
あまりの美しさに花が恥じらい、月が雲に隠れてしまう。絶世の美女を形容する中国由来の四字熟語。
桜梅桃李(おうばいとうり)
桜、梅、桃、李がそれぞれ独自の美しさで咲くように、他人と比較することなく、自分自身の個性を磨き上げ、自分らしく輝くべきであるという教訓。
棘がある(とげがある)
美しいバラに棘があるように、穏やかな言葉の中に、相手を傷つけるような悪意や皮肉が隠されている。
世の中の理・情景(勢い・変化・無常)
破竹の勢い(はちくのいきおい)
竹を割る際、最初の一節を割れば後は勢いに乗って一気に割れていく。止めることができない猛烈な勢いで物事が進む様子。
雨後の筍(うごのたけのこ)
雨が降った後に筍が次々と顔を出すように、似たような物事が相次いで現れること。新奇な流行や新しい組織が次々と生まれる状況をいう。
世の中は三日見ぬ間の桜かな(よのなかはみっかみぬまのさくらかな)
満開の桜があっという間に散るように、世の中の情勢は極めて移り変わりが早く儚い。昨日まで常識だったことが一変するような、変化の激しさを嘆く言葉。
一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる)
青桐(あおぎり)などの葉が落ちるのを見て秋の訪れを察するように、わずかな予兆や前触れから、物事の大局的な変化や結末を見抜くこと。
落花流水(らっかりゅうすい)
散る花と流れる水。春の景色が衰える様、あるいは物事が時の流れとともに消えゆく様子。転じて、男女が互いに慕い合う相思相愛の例えとしても用いられる。
花鳥風月(かちょうふうげつ)
四季折々の美しい自然の風景。また、それらを題材として詩歌や絵画を嗜む風流な心。
柳緑花紅(りゅうりょくかこう)
ありのままの自然の美しさ。または、それぞれの個性がはっきりと現れていること。
柳暗花明(りゅうあんかめい)
柳がしげり花が咲き乱れる春の情景。転じて、困難な状況を抜けた先に明るい展望が開けること。
草木も眠る丑三つ時(そうもくもねむるうしみつどき)
万物が寝静まった深夜。午前2時から2時半頃を指し、静寂を強調する際の定型表現。
鏡花水月(きょうかすいげつ)
鏡に映る花や水に映る月。目には見えるが手に取ることができない、儚い幻。また、言葉では表現しきれない余韻や趣の例え。
花に十日の紅なし(はなにとおかのくれないなし)
どんなに美しい花も十日と咲き続けることはない。栄華や美貌が長続きしないことの例え。
花に嵐(はなにあらし)
花が咲くと嵐が吹くことが多いように、良い事柄にはとかく邪魔が入りやすく、幸運が長続きしないこと。
状況の比喩・暮らし(意外・混雑・便り)
瓢箪から駒(ひょうたんからこま)
小さな瓢箪から本物の馬(駒)が飛び出すような、ありえない事態。意外な場所から意外な事実が判明すること、あるいは冗談が現実になること。
火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう)
猿にそそのかされた猫が火の中から栗を拾って大火傷をした寓話に由来。自分の利益にならないにもかかわらず、他人のために危険を冒して利用されること。
青菜に塩(あおなにしお)
青菜に塩をふると水分が抜けてしおれるように、失敗や叱責などで活力を失い、しょんぼりと打ちひしがれている様子。
梨の礫(なしのつぶて)
投げた礫(つぶて)が返ってこないことに「無し」を梨(なし)にかけた言葉。手紙や連絡を出しても、何の返答も音沙汰もない状況。
芋を洗うよう(いもをあらうよう)
桶の中で芋を洗う際に芋同士がぶつかり合うように、狭い場所に大勢の人がひしめき合い、激しく混雑している様。
鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる)
カモが料理の材料であるネギまで持ってくることから、自分にとって都合の良いことが重なり、思いがけない幸運が舞い込むこと。また、騙しやすい相手が自ら好条件を提示してくること。
根も葉もない(ねもはもない)
植物の根も葉もないような、何の根拠も証拠もないこと。全くのでたらめや、事実無根の噂話。
根掘り葉掘り(ねほりはほり)
根を掘り、さらに葉まで掘る(実際には葉は掘らないが強調)ように、物事の細部までしつこく、徹底的に聞き出そうとする様子。
徒花(あだばな)
咲いても実を結ばずに散る花。転じて、実質が伴わない計画や、成果の上がらない無駄な努力。
種を明かす(たねをあかす)
手品などの仕掛けや、隠されていた物事のからくりを明らかにすること。
鳩に豆鉄砲(はとにまめでっぽう)
豆鉄砲で撃たれた鳩が驚くように、突然の出来事に面食らって、目を丸くし、きょとんとしている様子。
胡麻をする(ごまをする)
すり鉢で胡麻をするとあちこちに付着するように、他人にへつらい、自分の利益のために機嫌をとる。
花が咲く(はながさく)
会話や雰囲気が一段と盛り上がり、にぎやかで楽しい状況になること。
竹馬の友(ちくばのとも)
竹馬に乗って一緒に遊んだ幼い頃からの友人。幼なじみ。
注意・教訓・失敗(油断・手遅れ・勘違い)
李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)
李(すもも)の木の下で冠を直そうと手を上げると、実を盗もうとしていると疑われかねない。人から疑われるような紛らわしい行動は、最初から慎むべきだという戒め。
花より団子(はなよりだんご)
風流な「花」を愛でるより、実利のある「団子」を好む。見栄えや名誉よりも、実際的な利益や実質を重んじる現実的な態度。
枯れ木も山の賑わい(かれきもやまのにぎわい)
枯れた木でもないよりは山が賑やかに見える。つまらないものでも、ないよりはましであること。※自分や身内を謙遜して言う。
六日の菖蒲十日の菊(むいかのあやめとおかのきく)
5月5日の菖蒲、9月9日の菊。それぞれの節句に間に合わなかった時期外れの植物。時機を逸して役に立たなくなった手遅れの状況。
木を見て森を見ず(きをみてもりをみず)
個別の木にばかり目を奪われ、山全体の広がりを把握できない。些細な部分にこだわりすぎて、全体の大切な部分や本質を見失うこと。
葦の髄から天井を覗く(あしのずいからてんじょうをのぞく)
細い葦の茎の穴から天井を覗き、世界を判断する。自分の狭い見識だけで、大きな物事や宇宙の真理を勝手に推測することへの皮肉。
独活の大木(うどのたいぼく)
独活は茎が大きく成長するが、柔らかすぎて材木としては使い物にならない。体ばかり大きく、実際には能力が低く役に立たないことのあざけり。
大根役者(だいこんやくしゃ)
演技力が乏しい役者。大根は消化が良く、食あたりをしない(当たらない)ことにかけた言葉。
言わぬが花(いわぬがはな)
全てを口に出して説明しない方が趣があり、差し障りもなくて良いこと。沈黙が価値を持つ状況。
木を隠すなら森の中(きをかくすならもりのなか)
あるものを隠そうとするなら、それと同じようなものが大量に集まっている場所に紛れ込ませるのが、最も発見されにくい最良の方法であるという考え。
柳に風(やなぎにかぜ)
しなやかな柳の枝が風を受け流すように、相手の勢いや抗議に逆らわず、巧みに受け流す。
木に竹を接ぐ(きにたけをつぐ)
性質の違う木に竹を接ぎ木する。前後がつながらず、不自然で調和がとれていないこと。
道草を食う(みちくさをくう)
目的地へ行く途中で、馬が道端の草を食べて立ち止まるように、他のことに関わって時間を浪費すること。
花を持たせる(はなをもたせる)
功績や名誉をあえて相手に譲り、相手が面目を保てるように配慮すること。
意外な効果・環境(健康・恐怖・影響)
柿が赤くなれば医者が青くなる(かきがあかくなればいしゃがあおくなる)
柿が実る秋は気候が安定し、かつ栄養豊富な柿を食べることで人々が健康になり、病人が減って医者の商売があがったりになること。
秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
美味しい秋茄子を嫁に食べさせないという嫁いびりの意、または茄子は体を冷やす、あるいは種が少ないため子宝を案じるという優しさの意。両説ある。
草木皆兵(そうもくかいへい)
敗走する軍勢が恐ろしさのあまり、風になびく草木までもが敵の軍勢に見えてしまう。極度の恐怖心から、周囲のあらゆるものに怯えること。
五穀豊穣(ごこくほうじょう)
米・麦・粟・豆・黍(きび)などの主要な穀物が豊かに実ること。農業の繁栄。
橘化して枳となる(たちばなげしてカラタチとなる)
南方の橘(たちばな)も北方に植え替えればカラタチになる。住む環境や周囲の人間関係によって、人の性質も良くも悪くも変化することの例え。
青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
新緑の鮮やかな緑色を見ることで、目の疲れが癒やされ、精神的にもリフレッシュされること。
枯れ木に花咲く(かれきにはなさく)
一度衰えたものが再び勢いを取り戻す。または、ありえない奇跡が実現すること。
錦上花を添える(きんじょうはなをそえる)
美しい錦の上にさらに花を置く。良いものにさらに良いものを加え、一層見事で華やかなものにすること。
一木一草(いちぼくいっそう)
一本の木と一本の草。その場にある全ての植物。転じて、極めてわずかなもの。
桃李もの言わざれども、下自ら蹊を成す(とうりものいわざれども、したおのずからこみちをなす)
桃や李(すもも)は何も言わないが、美しい花と実に惹かれて人が集まり、その下には自然と道(蹊)ができる。徳のある人のもとには、招かなくとも人が集まる。
草の根分けても(くさのねわけても)
草をかき分け、根元まで調べる。あらゆる手段を尽くし、どんな困難があっても目的のもの(主に人)を探し出す強い決意。
草葉の陰(くさばのかげ)
墓の下、すなわちあの世のこと。亡くなった人を偲んで、あの世から見守っているというニュアンスで使われることが多い。
両手に花(りょうてにはな)
二つの良いものを同時に手に入れること。または、一人の男性が二人の女性を左右に連れている華やかな様子。
茶を濁す(ちゃをにごす)
抹茶の点て方を知らない者が、お湯をかき混ぜてそれらしく見せる。いい加減なことを言って、その場を一時的にごまかすこと。
花道を飾る(はなみちをかざる)
引退や退職などの去り際に、華々しい功績を残し、周囲から惜しまれつつ誇らしく去ること。







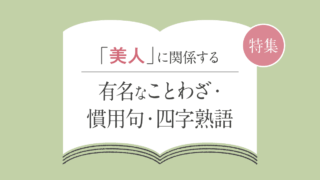
コメント