一生懸命に準備を進め、ようやく形が見えてきた時の達成感。
そんな日々の「料理」(りょうり)にまつわる道具や振る舞いは、古くから私たちの生き方や世渡りの知恵を映し出す鏡となってきました。
単なる調理の記録ではなく、先人たちが厳しい日常の中で培ってきた教訓や真理が、豊かな比喩となって現代の言葉に息づいています。
人間関係・絆を説く
同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
生活を共にしたり、一つの目標に向かって苦楽を分かち合ったりして親密な関係になること。
単なる知り合いではなく、同じ釜で炊いた飯を分かち合って食べた家族や同志のような、深い絆を象徴します。
糟糠の妻(そうこうのつま)
貧しい時代から苦労を共にしてきた妻のこと。
酒粕(糟)や米ぬか(糠)のような粗末な食事で食い繋いだ時代を支えてくれた配偶者を、出世した後も大切にすべきだという教えです。
手前味噌(てまえみそ)
自分で自分を褒めること。
昔は各家庭で味噌を造っており、自分が造った味噌が一番おいしいと自慢し合ったことに由来する言葉です。
食指が動く(しょくしがうごく)
ある物事に対して興味がわき、手に入れたいと思うこと。
ご馳走を前にすると人差し指が自然に動いたという古代中国の故事から、食欲以外の欲望や関心に対しても使われます。
失敗から学ぶ教訓
羹に懲りて膾を吹く(あつものにこりてなますをふく)
一度の失敗に懲りて、必要以上に用心深くなりすぎること。
熱い吸い物(羹)で火傷をしたのに懲りて、冷たい和え物(膾)まで吹いて冷まそうとする、過剰な警戒を例えています。
味噌をつける(みそをつける)
失敗して面目を失ったり、恥をかいたりすること。
大切な料理の仕上げに使う味噌を焦がして台無しにしてしまう、あるいは熱い鍋に触れて火傷をし、味噌を塗って治療したという不手際から生まれた言葉です。
煮え湯を飲まされる(にえゆをのまされる)
信頼していた人に裏切られ、ひどい目にあわされること。
安心して飲めるはずの飲み物として出されたものが、実は口を焼くような熱湯だったという状況から、深い裏切りによる痛みを表します。
お茶を濁す(おちゃをにごす)
いい加減なことを言ったりしたりして、その場を適当に取り繕うこと。
茶道の作法を知らない人が、抹茶をかき回してそれらしく見せたことに由来し、本質から目をそらしてごまかす様子を指します。
処世術と物事の本質
まな板の鯉(まないたのこい)
相手のなすがままになるしかなく、覚悟を決めるしかない状態。
調理台の上で、包丁を入れられるのを待つ鯉のように、自分の力ではどうすることもできない絶体絶命の運命を指します。
羊頭狗肉(ようとうくにく)
見かけは立派だが、中身が伴っていないこと。
看板には高級な羊の頭を掲げながら、実際には安価な犬の肉を出すという、客を欺く商売の様子が転じて、外見と実質の乖離を指すようになりました。
鼎の軽重を問う(かなえのけいじゅうをとう)
統治者の実力や、その地位にふさわしい人物かどうかを疑うこと。
鼎(かなえ)は古代中国の三本足の調理用鍋で、権威の象徴でもありました。
転じて、相手の実力を疑い、その地位を揺さぶる際に使われます。
毒を食らわば皿まで(どくをくらわばさらまで)
一度悪事に手を染めたのなら、中途半端にせず最後までやり遂げること。
どうせ毒を食べて死ぬ運命なら、皿まで舐めて満足しようという、破れかぶれな決意や徹底した姿勢を表します。
実利と価値の判断
餅は餅屋(もちはもちや)
物事は、その道の専門家に任せるのが一番であるということ。
素人が作るよりも、専門の職人がついた餅の方が確実においしいことから、プロの技術や知識を尊重すべきだという教えです。
花より団子(はなよりだんご)
風流や名誉よりも、実利や食欲を優先すること。
美しい桜を眺めることよりも、目の前のおいしい団子を食べる方を好むという、人間の本音を突いた表現です。
絵に描いた餅(えにかいたもち)
計画だけで実行が伴わず、何の役にも立たないこと。
どれほど美しく描かれた餅であっても、実際に食べることはできないことから、実現不可能な空論を戒める際に使われます。
画餅に帰す(がべいにきす)
せっかくの計画が、実現せずに無駄に終わること。
「絵に描いた餅」と同様に、空想上の満足だけで終わってしまい、現実的な成果が得られない残念な結末を表します。
暮らしと健康の知恵
医食同源(いしょくどうげん)
毎日の食事と病気の治療は、根源が同じであるという考え方。
薬を飲むことよりも、日々の食事を正しく調理し、摂ることが健康維持の基本であるという思想です。
一汁一菜(いちじゅういっさい)
ご飯に汁物とおかず一品という、質素な食事。
贅沢を慎み、分相応で簡素な生活を送ることの美徳、あるいは効率的で無駄のない暮らしを象徴します。
粗衣粗食(そいそしょく)
粗末な衣服と、質素な食事。
贅沢をせず、控えめで慎ましい生活を送る様子を指す四字熟語です。
腹が減っては戦ができぬ(はらがへってはいくさができぬ)
何をするにも、まずは十分な食事をとって準備を整えるべきだということ。
大きな目的を達成するためには、精神論だけでなく、身体的な力を蓄える現実的な支度が必要であるという意味です。
酒池肉林(しゅちにくりん)
極めて贅沢な宴会のこと。
池ができるほどの酒と、林に見えるほどの肉を並べたという、古代中国の贅を尽くした様子に由来します。

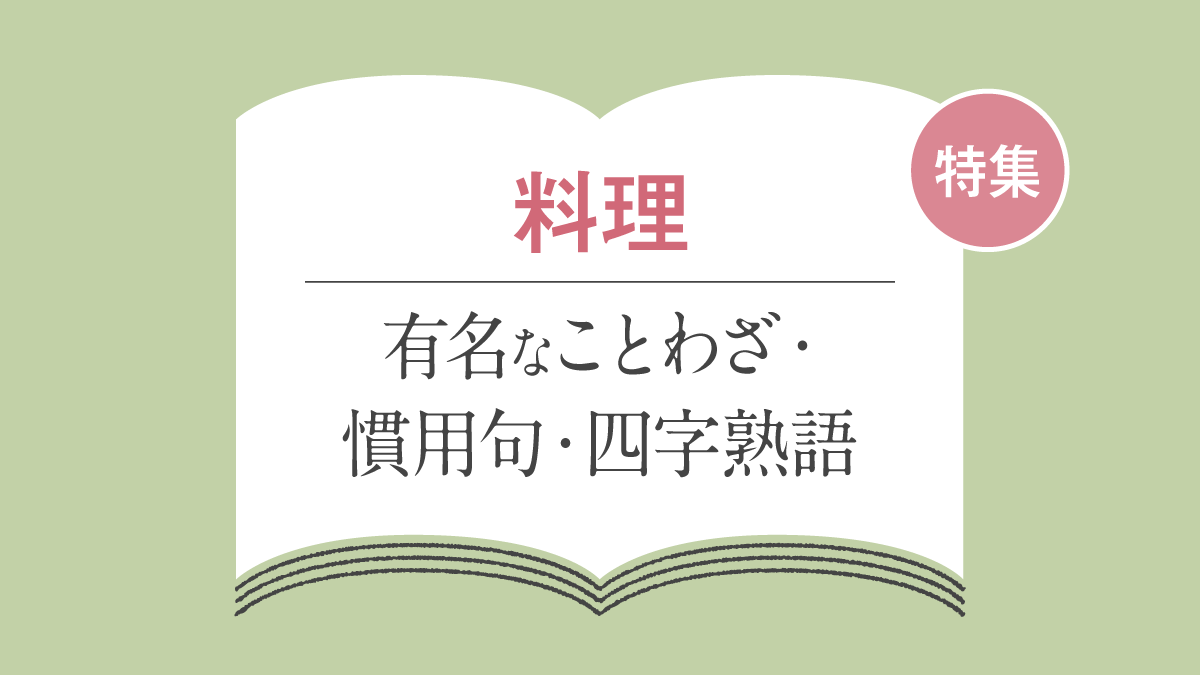


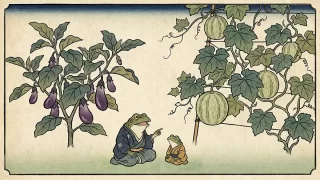





コメント